「蘇り」 真釣る木
- yamato-567
- 2020年5月19日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年6月7日
昔は兄弟姉妹が多かったため、戸籍謄本原本をとるとなりますと、五千円近くかかる方もおいでだと思います。
我が家が五千円越えとなりますのは、祖父が三度死んだためです。
ところで、人体蘇生と申しますと、何か胡散臭い話ですが、筑紫(熊本の宇土)から来た火の君(姫氏)が、その術式を使って生き返らせた話は、播磨国(姫路)風土記にあります。
その土地の地名は継となったとの事。 また、蘇りの術式は、継体でもあります。 神武天皇の蘇りなど、東征前の九州での古の天皇、もしくは斎王は、この継体の王であったのかも知れません。 ところが、熊襲タケルから継(火の君)を襲名した大和タケルは、草火をコントロールする、蘇りの剣である、草薙ぎの剣を使いきれず火に倒れます。 草薙とは、那岐と分けた曜玉です。 人体では、五臓六腑一性殖(五組連玉と二独玉で七岐)です。 それを真釣り合わし直すという事です。 それで、古代の真剣は真釣る木と申すのです。 ムラムラと湧き上かる叢雲の生命の木でもあります。 草叢から飛び立つ雉(霊)を、もう一度草(人体)に納める薙ぎの剣でもあります。 八咫烏で申せば、三本足を挙げて飛鳥と成ってしまった足を、再び二本を戻すという事です。 泡沫(歌方土)の淡(気流柔剛の火と水)と固まる淡路の秘め路は、ア行からワ行の、敷島に磯辺(五十音鈴)と幸拾う国(日本)の言霊でもあります。 祖母継乙女は亡くなりましたが、私のプロフィール写真では、古代、海へ入水した斎王の真似事をしております。 ちょうど、ミミズが入れものとなって土を通しますように、水瓶(魄)と成って、足比日口縄から手比日囗縄の握り(ニニギ)により、水(令)を通すのが人の生き宮です。 禊ぎの方法もそれに習います。 草薙の示しの写真は、お借りしています。


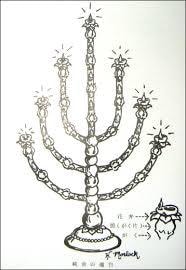






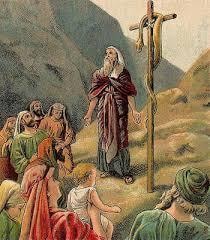



コメント